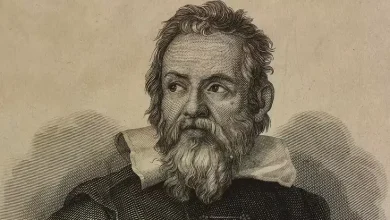第二次世界大戦中の太平洋戦争の一環として、1945年初頭、連合国軍はビルマ(現ミャンマー)海岸のマングローブ林で1,000人の日本兵を拘束した。日本兵のうち生還できたのはわずか20人だった。残りは先史時代の姿をしたイリエワニの大群によって生きたまま食べられただろう。連合軍司令官によれば、「あの夜は、ML(動力発射)チームのメンバーがこれまで経験した中で最も恐ろしい夜だった。漆黒の沼地に散乱するライフルの銃声と、巨大な爬虫類の顎に押しつぶされた負傷者の悲鳴が響き渡り、ワニが向きを変える不安を感じるような音は、地上ではめったに再現されない地獄の不協和音を響かせた。夜が明けると、ハゲワシたちがワニの残したものを片付けるためにやって来ました…ラムリーの沼地に入った約1,000人の日本兵のうち、生きて発見されたのはわずか20人ほどでした。」
この恐ろしい事件はラムリー島ワニ虐殺として知られており、1968年にギネス世界記録は約900人が死亡し、「ワニの襲撃による最も多くの人命死亡者」という疑わしい記録に認定された。
しかしここ数十年、歴史家や爬虫類学者たちはこの恐ろしい物語に疑問を投げかけている。ラムリー島の戦いで多くの日本兵が亡くなったことは明らかだが、公式の軍事報告書(英国であれ日本であれ)には「ワニの虐殺」についての言及はなく、イリエワニが「狂気の餌」として知られることもない。特に生きた人間の獲物においては、この規模での被害が顕著です。
それでは、この偽りの物語はどこから来て、どのようにして広く広まったのでしょうか?
コンテンツ
- 「ラムリー島虐殺」の起源
- イリエワニは人食いですか?
- ラムリー島の実話をつなぎ合わせる
- ワニが現場にいた
「ラムリー島虐殺」の起源
上で引用した恐ろしい一節は、水上から敵を偵察できる潜水兵士「フロッグマン部隊」のアイデアを発明したとされるカナダ王立中佐ブルース・S・ライトによって書かれたものである。
1945年、ライトはラムリー島に対するイギリスとインドの共同攻撃に参加したが、連合国はこの島を日本軍から占領し、戦略的飛行場として使用することを望んでいた。フロッグマン部隊のリーダーとして、ライトの仕事は偵察を行うことでしたが、サメやタコなどの地元の海洋生物の記録にも何時間も費やしました。戦後、ライトは尊敬される野生生物学者および作家になりました。
興味深いことに、ワニの大虐殺神話が大衆の想像力に浸透するのに貢献したのは、博物学者としてのライトの影響だったのかもしれない。
ライトは 1962 年の著書『Wildlife Sketches: Near and Far』の中でキラーワニに関する 1 段落の記述を書きました。しかしその後、この話は別の科学者である自然保護活動家のロジャー・カラスによって取り上げられました。カラス氏は1964年の著書「人間にとって危険」の中で、ラムリー事件を「これまで記録された中で最も計画的かつ大規模な大型動物による人間への攻撃の一つ」と呼んだ。カラスは次のように認めている。「もしその話がブルース・ライト以外の情報源から来たものであれば、私はそれを無視したくなるだろう。 [しかし]高度な訓練を受けたプロの博物学者であるブルース・ライトがラムリーにいました。」
問題は、ライトは厳密にはラムリーにいたにもかかわらず、巨大ワニに襲われた日本軍の悲鳴を聞いたと主張する目撃者の中にはいなかったことだ。彼の回想録「ビルマのフロッグメン」の後のバージョンによると、ライトは島を巡回しているボートの乗組員のイギリス人の同志からこの話を聞いたという。
この文章を注意深く読むと、ライトが虐殺を個人的に目撃したとは決して言っていないことがわかります。 「あの夜は、ML(動力打ち上げ)クルーのメンバーがこれまで経験した中で最も恐ろしい夜だった」とライト氏は三人称で書いた。しかし、自然界の注意深く観察者としてのライトの評判があったからこそ、彼の受け売り(そしておそらく粉飾された)説明が事実として受け入れられたのである。
イリエワニは人食いですか?
そう、イリエワニ( クロコダイルス・ポロサス )は、河口ワニとしても知られ、爬虫両生類学者のスティーブン・プラット氏によると、「定期的に人間を捕食する」2種のワニのうちの1つです。
イリエワニは体長7メートル、体重1トン(0.9メートルトン)以上に成長することもあり、ワニや小型のワニとは異なり、イリエワニは積極的に縄張りを守り、時折人間を襲います。 2021年にインドネシアで友人の目の前で襲われ食べられた不運な8歳の少女のように、毎年数十人がイリエワニによって殺されている。
イリエワニによる襲撃はどのくらい頻繁に起こるのでしょうか?イリエワニが生息する東南アジア、インド沿岸、オセアニアでは、2015年に合計180件のワニによる襲撃事件があり、そのうち79件が死亡した。
東南アジアやオセアニア全域で毎年イリエワニに殺される人が100人未満であることを考えると、900人の日本兵が数週間のうちに、ましてや恐ろしい一夜の間に貪欲なワニに生きたまま食べられる可能性はどのくらいあるだろうか?小さな島で?
歴史家のフランク・マクリンは、ビルマの戦いについての著書の中で、ラムリー島のワニ虐殺は「歴史的検証可能性のすべての規範に違反し」、生態学的論理にも反すると結論付けた。 「もし『何千ものワニ』が虐殺に関与していたとしたら」とマクリンは尋ねる(『アボカド』誌の記述によれば)、「これらの貪欲な怪物たちは以前はどうやって生き延びたのか、そしてその後もどうやって生き延びたのだろうか?」

ラムリー島の実話をつなぎ合わせる
ライトが報告したように、900人の日本兵がワニに食べられなかったとしたら、彼らはどうやって死んだのだろうか?
まず第一に、日本軍はラムリーで 900 人の兵士を失いませんでした。ナショナル ジオグラフィックの番組「ナチス世界大戦奇妙」と爬虫類学者スティーブン・プラットによる2つの調査によると、当初の日本兵1,000人のうち約500人がマングローブ林から生きて脱出できたという。この情報は日本の軍事アーカイブで発見されました。 (戦闘は 1 か月にわたって行われ、一夜にして起こったものではないことに注意してください。)
これによりラムリーでは依然として500人の日本兵が死亡したが、ワニの犠牲になった者はいたとしてもごくわずかだった。ラムリーの戦い中に生きていたビルマの地元村民(日本軍に徴兵された人も含む)によると、沼地での日本軍死傷者のほとんどは、暴露と清潔な食料と水の不足による脱水症状と病気によるものだったという。
それでは、1945 年 2 月の運命の夜にイギリスの海上哨戒隊が聞いたであろう恐ろしい音とは何だったのでしょうか?それにも答えがあるかもしれません。ナショナル ジオグラフィックの調査がアクセスした英国の軍事記録によると、1945年2月18日未明、ラムリー島とビルマ本土を隔てる海峡を泳いで渡ろうとする数百人の日本兵による「必死の試み」を連合軍が発見した。
「数人の水泳選手を除いて、横断中に生き残った人がいるかどうかは疑わしい」とイギリスの公式報告書は述べている(ナショナルジオグラフィックプログラムによる)。 「その夜、少なくとも100人の日本人が死亡または溺死したと推定されている…死者200人は控えめな推定値と考えられており、荷物を積んだボート約40隻が沈没したことが知られている。おそらくさらに50人の日本人がマングローブ林での暴露と食料と水の不足により死亡したと思われる。 14人が捕虜になった。」
これはおそらく本当のラムリー島の虐殺であり、血に飢えた捕食者によってではなく、ひどい戦争で人間の兵士によって行われたものです。
ワニが現場にいた
ラムリー島での日本人の死傷者の大部分は従来の原因によるものであったが、ワニの話にはある程度の信憑性がある。
スティーブン・プラット氏のチームが地元住民に聞き取りを行ったところ、10人から15人の日本兵が泳いで運河を渡ろうとしてワニに襲われ死亡した可能性があるとのことだった。別の連合軍司令官は、逃亡中の日本兵が本土に到達しようとして海軍の哨戒隊とサメの犠牲になったと報告した。つまり、少なくとも何人かの兵士が水中に潜む大型の捕食者によって殺されたという証拠がある。
そして、ラムリー島の神話の起源についての恐ろしい手がかりがあります。連合国軍が何百人もの逃走する日本兵を射殺した翌朝、イギリス軍は死者を餌にする日和見的な狩人たちが到着したことに気づいた。
英国の公式報告書は、「翌日は現場の恐怖をさらに高めるために暗い様子を見せた」と述べている。 「これまでめったに見られないと報告されていたワニが、運河岸に出現する数が増えている。」
Christopher Saunders と、ラムリー島の神話の間違いを暴いた The Avocado の記事に特別に感謝します。
もうこれは面白いですね
2017年、ギネスブックはナショナル ジオグラフィックの調査に基づいて、ラムリー島のワニ虐殺に関する記載を修正した。 「死者数がこれほど多くなるはずがないという説得力のある証拠を彼らが我々に示したとき、我々にはその記録を廃刊にする以外に選択肢はなかった」と編集長クレイグ・グレンデイは語った。